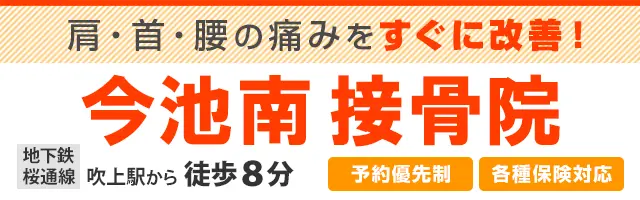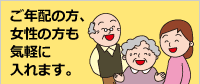オスグッド

こんなお悩みはありませんか?

膝の下の骨が盛り上がってきたように感じる
盛り上がった部分が赤くなったり、熱を持っているように感じる
運動中や運動後に、膝の下あたりに痛みが出る
ジャンプ・ダッシュ・キックなど膝に負担がかかる動作で痛みが出やすい
正座をすると膝に強い痛みを感じ、座ることが難しい
膝の曲げ伸ばしがしづらい・違和感がある
膝のお皿の下に痛みがあるが、我慢して運動を続けている
膝が内側に入り、X脚のような形になっているのが気になる
階段の昇り降りで膝まわりに痛みが出ることがある
このような症状がある場合、成長期に多い「オスグッド・シュラッター病(通称:オスグッド)」の可能性も考えられます。特にスポーツをがんばっている小・中・高校生の方に多く見られます。ご不安な方は、無理をせず専門機関へ一度ご相談ください。
オスグッドについて知っておくべきこと

オスグッドと診断された方へ ~無理は禁物です~
オスグッド(オスグッド・シュラッター病)と診断された場合、痛みを我慢して運動を続けることは避けましょう。無理をすると症状が悪化し、まれに強い炎症や骨の変形を伴うケースも見られます。場合によっては、長期の休養が必要となることもあります。
この症状は、小学生から中学生の成長期に多く見られますが、個人差があり、高校生や成人後に症状が現れることもあります。
どの年代でも、膝の下に違和感や痛みを感じた場合には、早めに専門機関での検査や相談をおすすめします。
また、痛みがあるうちは一時的にスポーツ活動を中止し、膝への負担を減らすことが大切です。症状が落ち着いたあとも、再発防止のためには慎重な運動再開が推奨されます。
一般的に、発症後3〜6か月の間は、運動によって痛みが出やすくなることがあります。
症状の現れ方は?

オスグッド病(オスグッド・シュラッター病)の特徴的な症状とは?
以下のような症状が見られる場合は、成長期特有の「オスグッド病」の可能性があります。
膝のお皿(膝蓋骨)の下あたりに痛みや赤み、熱感、腫れが見られることがあります。
お皿の下にある脛骨粗面(けいこつそめん)という部分が徐々に突出してくることがあります。
運動やスポーツを行った際に痛みが強まり、安静にすると痛みが軽減する傾向があります。
一度痛みが引いても、再び運動を再開すると症状がぶり返すことがあります。
膝を何度も曲げ伸ばしするなどの反復動作により、膝蓋靱帯(しつがいじんたい)が付着する部位に負担がかかり、炎症が生じることが主な原因とされています。
このような症状が見られる場合は、無理をせず早めの休養や専門機関での相談が重要です。
症状の進行を防ぎ、早期の改善を目指すためにも、適切なケアが大切になります。
その他の原因は?

オスグッド病の原因と発症について
オスグッド病は、スポーツ動作の繰り返しによって引き起こされることが多いです。特にジャンプ動作やダッシュ&ストップ動作、シュートやキックなどの膝に負担がかかる動きが原因となります。このような動きによって、**大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)**が過度に伸縮され、筋肉の柔軟性が低下します。特に成長期の子どもや青少年に見られることが多いです。
発症しやすい競技には、バスケットボールやバレーボール(ジャンプ動作が多いスポーツ)をはじめ、陸上競技や野球、サッカーなどが挙げられます。
具体的には、大腿四頭筋が膝の下の脛骨粗面という部位に付着しており、ジャンプなどで膝に強い力が加わると、その部分に微細な損傷が生じます。この損傷と回復の繰り返しが炎症を引き起こし、成長期の骨が過度に引っ張られることによって、膝の下に骨の隆起が生じ、痛みが発生するのです。
予防と対策
膝に痛みを感じ始めた場合は、無理に運動を続けず、安静にすることが重要です。早期の休養と適切なケアが、症状の悪化を防ぎ、回復を早めます。
オスグッドを放置するとどうなる?

オスグッド病を放置することで引き起こす可能性がある症状
成長異常が発生する可能性がある
オスグッド病を放置すると、骨や軟部組織に異常が起こり、成長過程に影響を及ぼすことがあります。特に、膝下の脛骨粗面部位が過度に引っ張られることで、骨の正常な成長が妨げられる可能性があります。
筋肉の付着部分が剥がれて離れてしまうリスク
大腿四頭筋などの筋肉が膝下の脛骨粗面に強く引っ張られることで、その付着部が剥がれてしまうことがあります。この場合、筋肉の付着部が骨から離れ、さらに治療が遅れると、症状が悪化することがあります。
剥離骨折のリスク
長期間にわたりオスグッド病を放置すると、膝の骨に過剰な負荷がかかり、剥離骨折を引き起こす可能性があります。これは、骨が完全に割れるのではなく、付着部が剥がれる状態です。
成長期における骨の成長の阻害
膝の成長が正常に行われないことで、成長期における骨の発育に支障をきたし、骨の形状や発育が変わることがあります。これが長期的な影響となり、成長が遅れたり、骨の不均衡が生じたりすることがあります。
成人後にも再発するオスグッド病後遺症の可能性
成長期に一度治癒したと思われるオスグッド病でも、成人後に再び膝の痛みが出ることがあります。特に、適切な治療を行わなかった場合や、完治したと誤解した場合に、成人になってからも後遺症として再発することがあります。
放置することのリスク
オスグッド病は、適切な対応をしないと症状が悪化し、長期的な健康問題を引き起こすことがあります。成長期の子どもや青少年においては、特に注意が必要です。症状が見られた場合は、無理に運動を続けず、早期に治療を受けることが重要です。
当院の施術方法について

治療の流れ
膝への負担軽減の指導
まず、膝への過度な負担が病気の原因となるため、無理に膝を動かすことを避けるよう指導します。また、スポーツを行っている患者様には一時的にスポーツを控えることをお勧めし、オスグッド病に対する理解を深めてもらいます。
筋膜ストレッチ
筋膜の柔軟性を高めるため、筋膜ストレッチを行います。この手法により、筋肉の張りを緩和し、膝の痛みや炎症の悪化を防ぎます。
アイシング(冷却療法)
症状が悪化している場合には、アイシングを行い、炎症を抑える治療を施します。冷却によって痛みや腫れを軽減することができます。
電気治療
電気治療(例: 微弱電流や低周波治療)を用いて筋肉の緊張を和らげ、血行を促進します。これにより、痛みの緩和や回復をサポートします。
O脚バンドの装着
O脚が原因で膝に余計な負担がかかっている場合、O脚バンドを装着することで膝の負担を軽減します。これにより、膝の歪みを改善し、痛みの軽減を目指します。
ハイパーナイフ(温熱療法)
ハイパーナイフは、特殊な機器を使用して筋肉を温め、血行を促進する治療法です。温熱治療により、筋肉の柔軟性が向上し、回復を早めます。
治療のポイント
無理な運動は控える: 痛みを悪化させないために、運動を一時的に休止し、膝への負担を軽減することが最も重要です。
再発防止: 一度改善しても再発しないように、柔軟性を高めるストレッチや筋力トレーニングを継続的に行うことが推奨されます。
これらの治療を組み合わせて行うことで、オスグッド病の症状を軽減し、早期の回復をサポートします。痛みが続く場合や症状がひどくなる前に、早めに治療を始めることが大切です。
改善していく上でのポイント

オスグッド病の原因と予防策
足関節の柔軟性不足
足首が硬い場合、しゃがみづらくなり、ジャンプ後の着地時に衝撃を膝で受け止めることになります。この衝撃を膝の筋肉で無理に緩和しようとするため、膝に過剰な負担がかかり、オスグッド病を引き起こすことがあります。
予防策: 足首の柔軟性を高めるために、足首のストレッチや足元を意識した運動を行うことが大切です。
膝の筋肉の柔軟性不足
膝周辺の筋肉が硬いと、膝にかかる負担を十分に吸収することができず、痛みを引き起こしやすくなります。特に、ジャンプやダッシュなどの動きが多いスポーツでは、筋肉の柔軟性を保つことが重要です。
予防策: 大腿四頭筋やハムストリングスなど、膝周辺の筋肉を定期的にストレッチすることで、柔軟性を向上させます。
初期段階での炎症を防ぐ
初期段階からの炎症が進行すると症状が悪化し、治療が長引くことになります。運動直後にアイシングを行い、炎症を早期に抑えることが大切です。
予防策: 運動後のアイシングや休息をしっかり取ることで、炎症を防ぎます。
適切なインソールの使用
足首が硬い場合、衝撃を吸収しきれないことがあります。靴の中敷きにかかとが高くなったものや、衝撃吸収に優れたインソールを使用することで、足元の衝撃を緩和できます。
予防策: 衝撃吸収性に優れたインソールを選び、足元をサポートすることが有効です。
運動前後のウォーミングアップとクーリングダウン
運動前にウォーミングアップをし、筋肉を温めて柔軟にしておくことはケガ予防に繋がります。また、運動後のクーリングダウンを行うことで筋肉の疲労を軽減し、早期回復を助けます。
予防策: 運動前後にストレッチを行い、筋肉をほぐすことでオスグッド病の予防に繋がります。
体の使い方の指導
特にジャンプ動作や着地動作を繰り返すスポーツを行う場合、体の使い方に注意が必要です。両足着地を意識するなど、膝に負担をかけない体の使い方を指導することが予防に繋がります。
予防策: 正しい体の使い方を習得し、膝への負担を最小限に抑えるよう心がけましょう。
オスグッド病の予防には、膝のケアだけでなく、足首や全身の柔軟性も大切です。日々のストレッチや体の使い方の見直しを行うことで、症状の予防や再発を防ぐことができます。
監修

今池南接骨院 院長
出身地:愛知県東海市
趣味・特技:服、サッカー、フットサル観戦、フットサルをやる